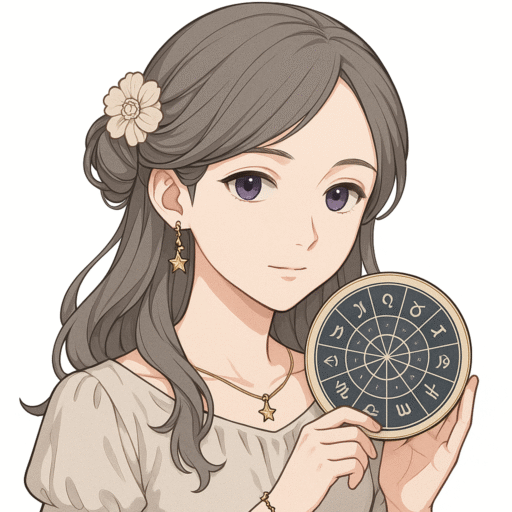遺骨を自宅に安置する「自宅供養」は、近年ライフスタイルの変化や墓地事情から選ばれるケースが増えています。
その際に気になるのが「風水的に大丈夫なのか?」という点。
ここでは、風水の観点から安心して遺骨を安置するための考え方と実践ポイントを解説しました。
自宅供養とは、ご遺骨を埋葬せずに自宅で供養する方法です。
よく似た供養方法に手元供養がありますが、この2つの違いは分骨をするかどうかです。自宅供養では全てのご遺骨を自宅で供養します。
目次
風水の視点から見た「遺骨の自宅置き」ポイント
自宅供養は風水的にNGではない
遺骨は「陰の気」を持つとされますが、清潔で静かな場所に安置すれば、必ずしも運気を下げるものではありません。
むしろ、家族にとって故人を偲ぶ心安らぐ場になるのであれば、ポジティブなエネルギーにつながるとも考えられています。
特におすすめの方角
- 東南(南東):太陽のエネルギーが入りやすく、良い「陽の気」を取り込みやすい吉方位。
- 明るく穏やかな雰囲気をもたらすため、安置場所に最適です。
避けたい方角・場所
- 鬼門(北東)・裏鬼門(南西):陰の気が乱れやすく、風水的に凶とされるため避けるのが無難。
- 水回り(トイレ・浴室など):湿気や不浄な気が溜まりやすい場所は不向き。
- 寝室や子ども部屋:感受性の高い人のそばでは心理的な負担となる場合もあります。
適した場所の条件
- 明るく風通しの良い空間:リビングの一角など家族が自然と集まる場所が理想。
- 清潔を保つ:供え物はこまめに交換し、空気や気の停滞を防ぐことが大切です。
安置時の実践ポイント
- 物理的安全の確保:骨壺は倒れにくい安定した棚や供養台に置きましょう。
- カバーや仕切りで結界を作る:視覚的にも気持ち的にも落ち着きが得られます。
- 日々手を合わせる習慣:気の流れを良くし、供養の心を養う大切な行為です。
心理的・文化的配慮
遺骨を「不運の原因」と考えるのは心理的な思い込みである場合も多く、「故人に見守られている」と前向きに捉えることが推奨されます。
また、来客時や小さなお子さん・ペットがいるご家庭では、扉付きの棚に収めるなど安全面への配慮も必要です。
宗教的・形式的な流れとの兼ね合い
自宅供養をどこまで続けるか(例:一周忌まで、三回忌まで)は、家族で話し合って決めておくと安心です。
宗派や信仰に応じた後飾り祭壇の設置方法もありますが、これは風水ではなく宗教・文化的な観点に基づくものとなります。
まとめ:風水的に見た「自宅供養のベストプラン」
| 要素 | 良い点・ポイント |
|---|---|
| 方角 | 東南(南東)が最良。南や東寄りでも問題なし。 |
| 置き場所 | 家族が集まる明るく風通しの良い空間(リビングなど)。 |
| 避ける方角・場所 | 鬼門(北東)、裏鬼門(南西)、水回り、寝室・子ども部屋。 |
| 設置方法 | 安定した棚・供養台に、カバーや扉付きの収納で安全かつ落ち着いた雰囲気に。 |
| 日常の供養習慣 | 毎日手を合わせ、供え物を清潔に保つ。 |
| 心理的配慮 | 不安を感じる場合は目に付きにくい場所へ移動するのも選択肢。 |
| 文化的配慮 | 宗派や家族で供養方針を共有し、将来の混乱を避ける。 |
最後に
風水は「心地よく暮らすための指針」であり、絶対的なルールではありません。
大切なのは「あなたやご家族が安心でき、故人を敬える空間をつくること」です。